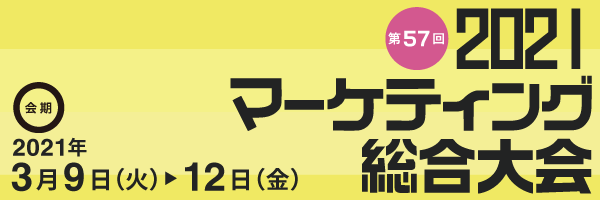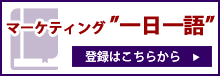これからは、すべてのビジネスマンがプロデューサー型にならなければいけないということです。
株式会社マーケティングプロモーションセンター代表取締役で、JMA専任講師を務めておられる岡本正耿講師からお話を伺いました。
一般社団法人日本能率協会の中川雅志がインタビューします。(以下敬称略、役職当時)
最近のマーケティングの大きな流れとは?

中川
ありがとうございます。
最後の質問になりますが、セミナーの中で、「マーケティングは哲学だ」というようなことをおっしゃっていました。
あの意図を少しご説明していただけないでしょうか。
岡本
考えることというのを突き詰めていくと、一番根幹みたいなところに全部ぶつかってくるのですね。
例えば「認識というのはどういうこと?」とか。
同じものを見ても、ある人はこれをチャンスと認識し、別の人は、これは無理だと認識する。
認識というのは、ものを見てどう感じるかですよね。
ところが、厳密に言うと、認識というのは、ものの捉え方という哲学用語なのです。
実は今、マーケティングも、機械論から生命論へと大きな流れが生まれていると言われています。
機械論というのは、テクニカルに、マシンと同じようにビジネスを捉えるからできるのです。
分析して、分けていく。
でもそうではなくて、人がどう感じるか、感じるということと、感じながら何か行動をする、その行動が変化する、そういうことってなんだろうというように、そちらを掘り下げていこうとする流れが生まれています。
するとどうしても計算型の機械論ではなくて、類推をしたりストーリーを想像したりといったものが必要になります。
そうすると、いろいろな人がおっしゃっていましたが、経営学、経済学より言語学の時代と言われていますが、そういったものがマーケティングにも欠かせなくなってきているのではないかと思いますね。
こういったところが、マーケティングは哲学だ、という言葉の意図です。
中川
よく、左脳から右脳へというふうにおっしゃいますけれども、ああいうイメージでしょうか。
岡本
いや、そこもまた変わってきてしまいます。
実は、左脳と右脳は別々ではないということがわかってきたのですよ。
どういうことかというと、右脳で受け止めていることが左脳でロジカルに反応されて、また右脳に戻ったりしている。
右と左の協力関係があるということが脳科学で発見されて、かつてロジャー・スペリーが提言した右脳左脳というものが、実はこうだよと、より具体的なことがわかってきた。
今までの仮説的理論が、実はこういう背景があると説明されると、ならばこのような新しい解釈が成り立つね、どんどんと新しい仮説が生まれていく。
今まであいまいだった領域がわかってくればくるほどです。
なぜiPodが売れたのかといったような説明は、言語学的説明に位置付けられます。
ストーリーが大事とか、コンテクストが大事と言われているのは、全部言語学的な解釈です。
そういう意味では右脳左脳とは違うんですね。
中川
本日は、どうもありがとうございました。
岡本
ありがとうございました。